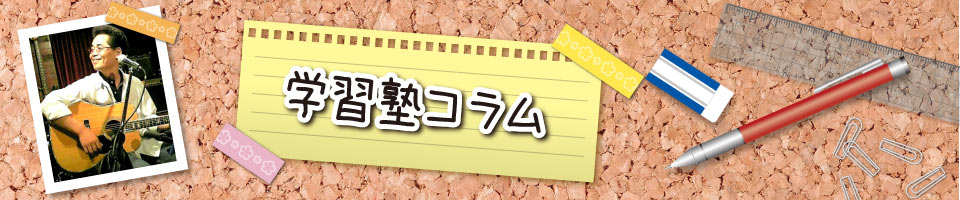先日、学習塾の倒産について記事が出ていました。2024年は史上最悪の40件が倒産したとのこと、やはり胸が痛みます。その教室業務に従事している人々やその教室が気に入って通っていた生徒さんの気持ちを思うと。。。
そして2025年は1~9月期だけで37件だそうです。年末までに最悪を更新してしまうのは目に見えています。ウ~ン。。。
小規模資本の学習塾が倒産の主役になっている分析が出ています。これは大手寡占になってしまうことを意味します。これって。。。
学習塾に限らず、多様な運営形態(大手、準大手、中小、個人、等々)があるから健全に運営されます。考えてみてください、『あなたのお子さんが通える塾は大手の●●か△△ですよ』しか選択肢がなくなっていたら。。。
残念ながら今の世の中に学習塾は欠かすことのできない要素になっています。学校だけでは補完できなくなっているからです。特に受験となると学校のみの対応で高度な受験に臨めば。。。
それでは逆転の発想で学校だけで受験などが完結し、塾不要の世の中になれば。。。これも夢物語です。先日公表された『学校教職員働き方改革』の中間報告では先生方の担う強度な負担は未だに改善されていません。
当教室のような小規模事業主はそろそろ根本的な改善をすべき時期にいるように思います。学習塾事業者は得てしてお山の大将的発想の持ち主が多いのですが、いつまでも井の中の蛙ではいけません。
私が以前いた旅行業界では『ハウスエージェント』という営業形態がありました。出張や社員旅行・視察旅行などの旅行に自社内に設けた旅行会社を使うシステムです。勿論外部者が使うこともできるところが多かったように思います。
塾業界がこれを模すことは出来ませんが、せめて母体小中学校の学区内にある塾が協力、場合によっては小中学校とも手を取り合って運営するのも一手段です。連携を取ることによって生まれるメリットは大きいと思います。
しかしこれには規制の壁が大きく立ちはだかります。日本版DBS導入も必須となるでしょう。学校側としても諸々の基準作りが必要になります。
その基準も現場で作るのか、都道府県や国が作るのかで大きな問題になります。現場で作るのが一番現実的、ニーズに即していると思います。しかしこれ以上の現場負担は非現実的です。
都道府県や国が作ることは現場への負担を大きく減らすことになるかもしれません。しかし無理ですよね! 現実問題として私立高校無償化という立派な施策がありますが、これは未だに何の決定もされておらず、私立高校を戸惑わせています。
授業料という学校経営の根幹を担う問題ですらこの状況、それなら他のことをやらせても結果は見えています。所詮は政治家の人気取り政策だったのでしょうか。。。
それなら…
学習塾が動くべきでは。。。と考えています。私は『自教室だけ良ければいい』とは考えていません。近隣の塾も繁盛し、地域の生徒さんを伸ばすことによって学区全体が盛り上がるべき、そうすれば自教室の生徒さんも切磋琢磨の中で伸ばせるはず。。。
多分に『スタンドプレイだ!』と言われるような行為ですが物事が始まるときの軋轢はつきものです。それならそんな声を気にせずにやることも一考です。
旅行会社時代、上司からよく受けた指導が『蛸壺に入るな!』でした。視野を広く取ること・一人で抱え込まずに周りを頼ることを諭されました。教室という蛸壺に籠らず、フラットな気持ちで取り組みたいと思います。
来たれ! 秋期入会生!!