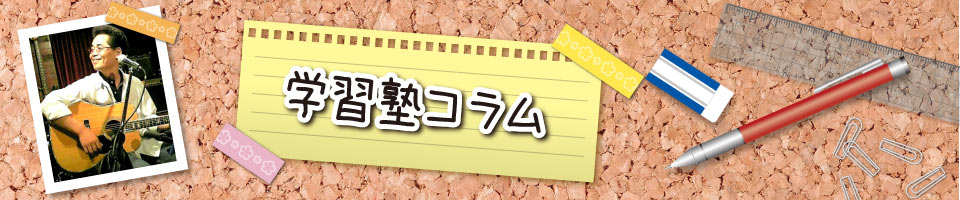本章は前章より続いています。
教育の平準化は受ける側にも問題があると思います。昨今の学校に対するクレームです。これが度を超えると下限に併せるシステムを採用せざるを得なくなると思います。
『A先生はやってくれるのにB先生は出来ないの!?』『C先生の授業は分かりやすいのにD先生の授業は分かりにくい』、このクレームを防止するには上方に揃えるより下方に併せた方が合理的です。短絡的ですが…
結果として『分かりやすい授業を!』『より良いクラス運営を!』と工夫しても出来ていない方に基準が置かれるためにその努力が報われない状況が起こるのです。
度を超えたクレームの原因の一つに学校や教員の権威失墜があります。これは色々な問題が複雑に絡んでいるのでここでの言及は避けます。ただ、それが巡り巡ってデメリットを被るのは学生の皆さん、つまり将来の日本です。
私たち大人はそろそろこのことについて真剣に考えなくてはなりません。個で考えても行政主導で考えても歪みが出ます。それなら社会全体で教育を支えていくことが求められると思います。
その上で学校の先生方が各々工夫した成果を授業で表現できる環境づくりこそがこれからの世の中には必要だと思います。個が切磋琢磨していくことで集団の力が向上し、その集団が切磋琢磨するようになると。。。
話が大きく逸れましたが新任の先生が今お持ちの志を最後まで貫ける環境が望まれます。そのためにはまず学校自体が官僚主義を止め、私たち大人もその環境づくりを援助すべきです。
そんな世の中になれば教育は必ず上向きになります。教育が機能すれば社会が豊かになります。疑われる方もいらっしゃいますが…それが本来の教育の目的では!?
来たれ! 新入会生!!