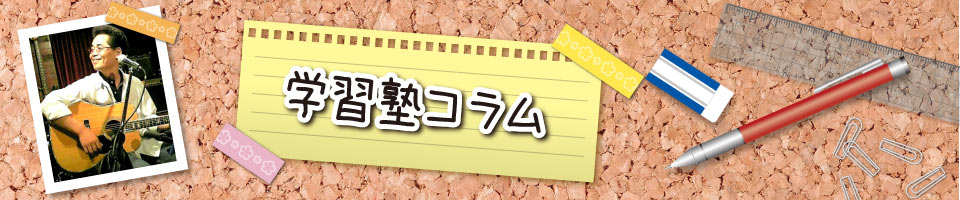先日、ある私立高等学校の校長先生にお話をお伺いする機会を得ました。お付き合いも長くなっているので普段の悩みや疑問点などを率直にご指導頂けるありがたい時間でした。
その中で教室の生徒さんに読書習慣がつかないことを悩んでいると打ち明けたところ、頂いたご助言はまさに金言、目からウロコでした。物事に対して角度を変えて俯瞰する大切さを再度認識しました。
『読書習慣は高校でも大きな課題。でも一朝一夕には育たないものです。』『高校だけではなく、小学校や幼児教育でもその重要性はもっと認識されるべきです。』『生徒さんは日々読書! と言われている筈です。』
『しかしそんな状態でセンセ~(私のことです)からも本を読むよう指示・指導されたら生徒さんはどう思いますかね!?』『きっと心の中で舌打ちしている筈ですよ!』『反感を生むだけです。』
『それならいっそ生徒さんにも入試のためと割り切って読書させることも一方法かもしれません。』『センセ~の入試問題分析でどのような出題傾向が出ているのかは既に把握されているようなので。。。』
『これが入試に活きる、そんな本を推してあげると上手く滑り出すのでは!?』『本を読め、ではなく、本を用意してそれをどんな目的でどのような意識で読むか迄指導してあげるとあとはスムーズですよ。』
そうか…これまでは押し付けで読書を強要していただけだった、だから読書習慣を習得させられなかったのか。。。まさに青天の霹靂でした。
ここまで大ヒントを頂けたなら次は私が行動に移す番です。ここ数年の入試では現代文の古典(変な言葉ですが。。。)と言われる明治~昭和初期の文豪物はほぼ出題されません。それなら頻出分野を集めれば良いのでは…!!
今春から中3及び中学受験の小6生諸君にはそれらの本を一定期間で読み切ることを課題として取り組んでもらっています。既に興味を持ち始めている生徒さんも散見されます。
秋ごろまでに10冊くらい読み切れれば今年の受験は国語の対策・記述対策・思考力を問う問題対策が大きく変わるように思います。また、集中力を持続させる力がつけば演習効率自体が変わるのでは。。。
私が受験産業に関わってからすでに数十年、当教室を管理するようになって15年目です。しかしこれからも試行錯誤の日々が続くことは間違いありません。でも、悪くないことだと思うのです。
試行錯誤、言い換えれば『前年度と比べてもより良い授業を提供する』行動は常に持ち続けたいと思います。それが絶えず変動する入試に対応することだと思います。
来たれ! 新入会生!!