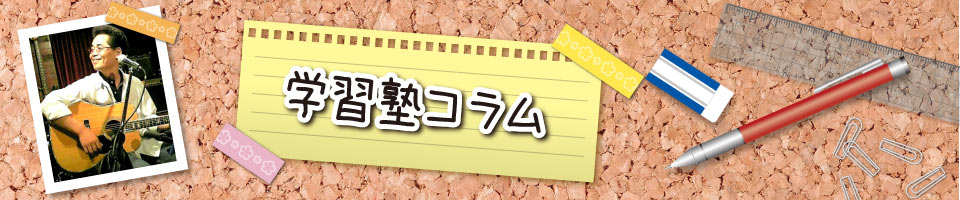2011年3月11日の東日本大震災から14年が経ちました。あっという間のように感じます。しかし歳月は確実に流れています。
新中3生は2010年生まれです。それはすなわち震災の記憶が殆どない生徒さんばかりということです。私の感覚としては大震災後の混乱はつい先日のような感じもしますが。。。
授業中でも折に付け大規模災害と防災についての2面を生徒さんに話してあげるべきではなかろうかと思っています。どちらかだけではやはり不健全。それなら両輪で伝えたいと思います。
近年は学校での防災教育も長足の進歩を遂げ、生徒さんも関心を持って学んでいる様子がわかります。民間の防災教育行事が入り込む隙がないほど、と言われています。
しかしこのような題材こそ学校と地域が共生して取り組むべきことです。これ、2024年1月1日に起きた能登の地震で避難生活を送っている同級生(学校教員)が洩らしていました。
『普段から連携を頭に入れていないから必要な時に機能しない』『単独でやっていると個々は有意義なことでも結合すると重複や齟齬がある』などの感想を持っていました。
確かにその通りです。常日頃から意思の疎通を図っていなければ緊急時の混乱は目に見えます。だからこそ『学校は学校』『地域社会は地域社会』ではなく一体となって行うのは当たり前です。
2011年3月11日は金曜日、2025年と同様にこてはし台中学校の卒業式でした。穏やかに晴れ渡った卒業式日和でした。それが午後2時46分に一変しました。
当日の記憶はだいぶ散乱してきました。ただ、卒業式で一旦下校した後に部活のために再登校しようとした生徒さんがいました。あの状況下だったので帰宅するよう促しました。中学校へは私から電話した記憶があります。
教室では情報収集が難しかったのですがWEBで未曽有の大災害と推測できました。教室の一時運営停止と授業の一時停止を一斉メールで配信したのを記憶しています。
当時、この教室は会社運営だったのですが、通信手段がなかった(電話は殆ど通じませんでした)ため、各教室で判断しなければなりませんでした。
中には授業を強行しようとした教室もありました。しかし安全が担保されない中で授業を行う必要性は…私は感じません。そんな議論がメールのやり取りで行われたことを覚えています。
そんな中、通塾していた生徒さんやご家庭からのメールも相当数ありました。『週明け、学校はあるのかな!?』そんなお問い合わせでした。当時は学校の一斉メールもあまり機能していなかったように記憶しています。
生徒さんの中には上記のように学校に行くこともあったと思います。中学生には『安全確保』より『学校の決まり』を遵守する傾向にあります。だからこそ地域との連携が不可欠と思います。
これは『中学校の指示が…』という意味ではありません。地震発災前の指示(再登校)に従うべきかの判断を地域ぐるみですべきではなかったかと思っています。
LS WILLでは安全運営を最優先します。近年では天候状況(台風や大雪警報など)で授業を停止しています。生徒さんの安全と引き換えに行う授業に意味はないと考えています。
その上で学習塾総合保険にも加入しています。お金で解決できるとは思っていませんが教室での学習中や通塾時・帰宅中に何かあった時の備えとして必要と考えています。
しかし結局は心がけだと思います。安全な教室運営、すなわちお子様を安全にお預かりすることは最低条件だと肝に銘じて運営しています。
来たれ! 新入会生!!