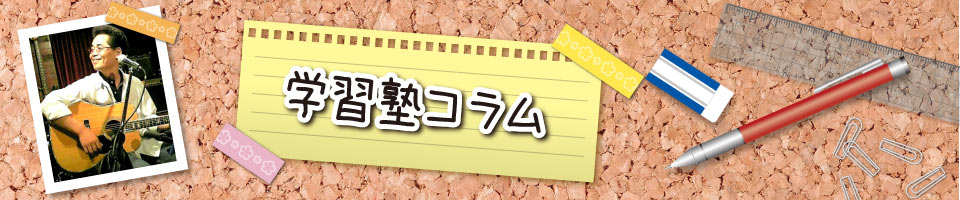まだまだ2025年入試問題の総括には時間が掛かるのですが、作業自体は順調に進んでいます。この時期は頭の中をまっさらにして意識が更新できる時期でもあると思っています。
公立私立を通じて顕著な科目は国語だったのではないかと思っています。私立高校入試では理科社会がなく、数学英語共に大きな変革期が一段落したから、とも言えそうですが。。。
国語は巷間声高に叫ばれているようにより一層の読解力が求められていますが、一方では問題文の易化も進んでいるように感じます。そのギャップは正確に捉えたいものです。
国語の読解問題というと最初にイメージされるのは『漱石』『芥川』など明治~昭和初期文学書の対策…ではないでしょうか。事実、今でも教科書では幅を利かせています。
しかしそういった古典的出題(と言ったらいいのでしょうか)はかなり少数派となりました。それなら今の主流は…?
現在の主流は2000年代・2010年代以降の文学書です。これらは今のライフスタイルに立脚して描かれる物語なので内容把握もしやすく、共感も得やすいものです。
しかし、一口に2000年代・2010年代以降の文学書と言っても星の数ほどあります。そこでもう一つの共通点が必要になります。それが文学賞です。
文学賞で有名なものとして『芥川賞(純文学)』『直木賞(大衆文学)』があります。大賞受賞作や候補作品からの出題が意外なほど多かったのは驚きでした。
千葉県の公立高校入試問題で出された三浦しをんさんも2005年に直木賞候補、2006年に直木賞を受賞しています。他にも本屋大賞などの受賞歴があります。
対策を間違えて上記の『漱石』『芥川』で学習してしまうと現在の入試には立ち向かえなくなります。いくつか事例を挙げてみましょう。
まず親しみやすい文章だからフラットな視線で意見が述べやすいこと。前述の『古典的出題』となってしまうとそれに対する意見も出尽くしていて受験生はそれを『下からの目線で』対応せざるを得ません。
また、読み易さ(文章構造のシンプルさ、言葉の平易さ)も着目すべき点です。それによって問題自体易化し、その反動で問題文が長くなる・設問が多くなるなどの対策も求められます。
国語の入試問題については他にも古文や言語事項についても大きく変わっています。そちらについては…教室で実物をご覧頂きながら説明したいと思います。
LS WILLは『学習は要領よく効率よく』をモットーとしています。それはデータ分析に裏付けられたものです。受験生やそのご家庭が実際に出された入試問題・過去問を消化しきるには限界があり、教室でお手伝いしているのです。
受験勉強は膨大な量を消化しなくてはなりません。無駄…ではありませんが効率が上がらないことに対してことさら厚く対応するのは如何なものでしょうか。
シンプルに最短ルートを取る、それがLS WILLの受験スタイルです。
来たれ! 受験生!!