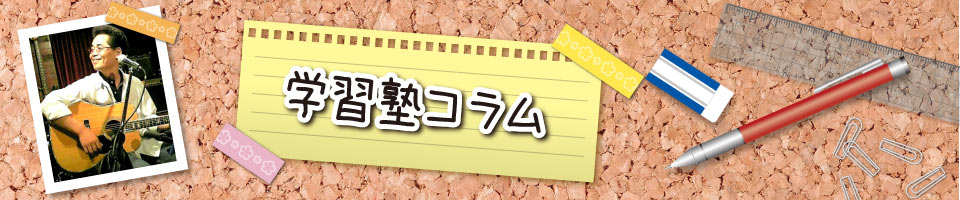2025年度入試も終盤となりました。これからは入試問題や出願傾向を分析する段階に入ります。その上で生徒さんがそれぞれ持っている志望校入試を突破するための方策を練ってカリキュラムに反映させる作業に入ります。
昨今は入試問題も大きく変わりました。英語では会話文が外せない対策要素となっています。国語では読み書きの力はもとより意見を集約・要約する力が求められます。
理科社会は従来の短答型から実験やフィールドワークを通した課題解決型の出題に代わっています。しかしそちらばかりの対策では対応できず…と言った傾向を示しています。理科社会はもうしばらく変わりそうです。
一番変わっていないように見える数学ですが、実は大きく変わっています。千葉県問題を例にとると『大問1で点を稼いで…』は簡単なことではなくなっています。逆に関数や作図は易化する傾向があります。
また、確率やデータの活用は今や対策必須の単元となりました。それまでは小問対策程度の片手間で済んだのですが、大問として独立した対策が求められるようになりました。
こういった問題対策、当教室が会社組織で運営されていた時期は会社で行いました。現在は全て私自身の目で見て頭で考えて…とやっています。正直に言えば大変ですがメリットは計り知れません。
一度解けば頭の片隅に残ります。それが授業で指導しているさなかに頭をかすめれば生徒さんに『こんな問題が実際出されたんだよ!』と伝えてあげることが出来ます。
それを聞きかじりの情報に頼ってしまうと自分自身が未消化なので生徒さんや保護者様に細かいニュアンスまで伝わらないことがあります。自分で実際に目を通せば説得力が違ってくるような。。。
演習時間についても問題ボリュームを考えて『この問題は〇分で解こう』『このページは。。。』として指導することも容易です。いくらきっちり解けても時間切れでは意味がありません。
何度も言いますが正直なところ面倒と思うこともあります。公立・近隣私立高校(それも1校で数パターン)の問題に全て目を通すことが前提になるからです。しかし、面倒だからこそ頭に残るのかなと思います。
会社運営時同様に今でも手を掛けずに進めようと思えば春の入試問題解説の勉強会(例年5~6月に開催されます)に出席すれば良いことです。しかしそれを待つのは横着かな。。。
勉強会の席はあくまで答え合わせとして、教室の生徒さんにいち早く情報還元するためにもまず自力で解いて自己流の分析をすることが大事だと思います。
自己流の分析と言っても決して見当違いではないと思っています。それが指導の道しるべになるものと確信して取り組んでいます。
『入試情報が少なくて不安。。。』とお考えの皆さん、教室までお運び頂ければこれらは全てご覧頂くことが出来ます。お気軽に教室までご連絡ください。
来たれ! 新入会生!!